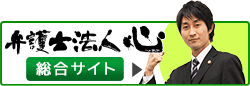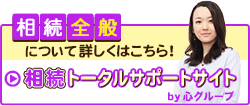本ブログをご覧いただき、ありがとうございます。
弁護士・税理士の鳥光でございます。
前回に引き続き、一軒家と比較した場合の、相続人不存在区分所有建物の管理、処分するうえで注意すべき特徴についてお伝えします。
一軒家と比較した場合の、区分所有建物の特徴は次のとおりです。
①老朽化しにくく価格の下落が緩やか
②基本的に境界の問題はない
③バルコニーや玄関扉の一部など共用部分への配慮が必要
④管理の開始時や売却時などに管理組合への手続きが必要
⑤総会決議等への参加が必要
個体差もあると思いますが、区分所有建物は一軒家と比べ、外部と接している部分が少なく、共用部分は管理されていることから、老朽化しにくい傾向にあると感じます。
庭がないものも多く、擁壁もないため、価格が下落する要素が少ないです。
基本的に境界確定の問題もありません。
一軒家と異なる点のひとつに、共用部分への対応があります。
バルコニーに残置物がある場合、他の住民の方へのご迷惑にならないよう、撤去します。
玄関扉に対して何らかの作業をする場合には、場合によっては管理組合との調整が必要になるため、事前に管理規約の確認も行います。
相続財産清算人に選任されたことについては、管理組合へ伝え、必要な届出書類も提出します。
このようにすることで、管理組合と連絡を取り合えるようになります。
区分所有建物を売却する際にも、管理組合への届出が必要となるため、事前に必要書類の確認をしておきます。
売却するまでの間に総会が開催される場合には、基本的には議決権の行使をします。
(相続人不存在となった空き家の存在が引き起こす問題のひとつに、総会決議が行えないことがあります)
議題の内容が、相続財産の一部処分や大きな変更が発生するものである場合、事前に裁判所に確認をしたり、許可を得ることも必要と考えられます。