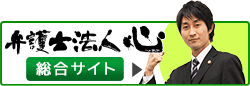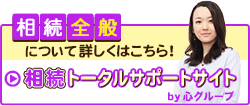弁護士・税理士の鳥光でございます。
本ブログにアクセスしていただき、ありがとうございます。
今回は、消火器具の設置が必要な防火対象物についてのお話です。
消火器具は火災の初期段階で素早く消火活動を行うための重要なものです。
消防法では、建物の用途や規模に応じて、消火器具の設置が義務付けられています。
なお、消火器具には、消火器と簡易消火用具がありますが、実際には消火器が設置されることが多いです。
まず、防火対象物とは、火災が発生した際に人命や財産に重大な被害が及ぶ可能性がある建物や施設のことで、具体的には、消防法施行令別表第1に定められた学校・病院・劇場・店舗・事務所・工場・共同住宅などが該当します。
(※本ブログ公開時点)
設置義務の有無は、主に防火対象物の延べ面積・用途・構造などで判断されます。
例えば、映画館やカラオケボックス、入院施設のある病院、地下街などは、延べ面積に関係なく消火器具の設置が必要となります。
百貨店や幼稚園、共同住宅などは、延べ面積が150㎡以上の場合に消火器具の設置が義務付けられます。
小学校や図書館、事務所などにおいては、延べ面積が300㎡以上の場合に消火器具を設置しなければなりません。
また、電気設備がある場所や、多量の火気を使用する場所にも設置が必要です。
設置にあたっては、見やすく取り出しやすい場所に配置し、標識を掲示して誰でもすぐに使用できるようにしておくことも大切です。