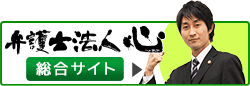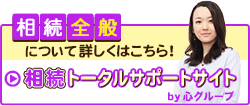弁護士・税理士の鳥光です。
今回も本ブログをご覧いただき、ありがとうございます。
士業を含め、建物などを使って事業を営む際には、防火に関わる様々な対応が必要とされます。
私自身、防火管理者講習を受講したうえで、防火管理者となっています。
法律に基づいた、定期的な消防用設備等の点検も行われています。
今回からは、防火、消防に関する知識や実務について、法律を交えながら紹介していきます。
まず、消防法に登場する「防火対象物」、「消防対象物」、「関係者」、「関係のある場所」という用語についてです。
① 防火対象物
「防火対象物とは、山林又は舟車、船きょ若しくはふ頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物若しくはこれらに属する物」と定義されています。
火災予防の観点から、特に防火上の配慮が必要とされる建物や施設を指します。
劇場や遊技場、病院、ホテル、百貨店など、多くの人が利用し火災時に被害が拡大する恐れのある施設が該当します。
② 消防対象物
「消防対象物とは、山林又は舟車、船きよ若しくはふ頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物又は物件」と定義されています。
消火活動の対象となるものが広く含まれますので、建築物以外の「物件」(例えば、家具や機材など)という表現がなされています。
③ 関係者
「防火対象物又は消防対象物の所有者、管理者又は占有者」と定義されています。
消防法では、関係者に対して、設備の設置、点検、報告などの義務を課しています。
④ 関係のある場所
「防火対象物又は消防対象物のある場所」と定義されています。
消防計画や避難計画を作成する際には、関係のある場所がどの範囲に及ぶかを考慮に入れる必要があります。