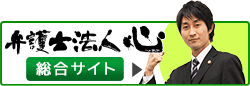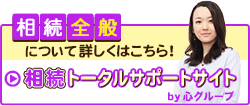今回も本ブログをご覧いただき、ありがとうございます。
弁護士・税理士の鳥光です。
相続人不存在となった空き家には、大きく分けて一軒家と区分所有建物があります。
今回と次回に渡り、それぞれについての管理、処分するうえで注意すべき特徴を、経験に基づいてお伝えしていきます。
まず、一軒家についてです。
ここでは、家屋とその敷地が、どちらも被相続人の所有であったものと仮定します。
区分所有建物と比較した場合の、一軒家の特徴は次のとおりです。
①家屋は古くて価値は低いことが多い(解体費がかかることも)
②隣地や道路との境界確定書を発見できないことがある
③庭がある場合には草木の手入れや害虫対策が必要
④宅地擁壁が老朽化していると売却価格が大きく下がることがある
⑤隣接している私道の所有権(共有持分権)がないか調査が必要
感覚的には、一軒家の方が価値が下がりやすい傾向にあると思われます。
特に、家屋が空き家になってから長期間が経過していると、屋根や壁、塀などが傷ついていて、再利用が困難です。
そのため、現実的には家屋の解体を前提とした、いわゆる古屋付き土地として売却することもあります。
更地にするための費用を織り込んだ売却価格となるため、土地自体の価格よりも低価格での売却になります。
盛り土がされていて、宅地擁壁がある場合には、より注意が必要です。
築年数が古い一軒家の場合、擁壁が崩れていることや、技術要件を満たさない擁壁であることがあります。
擁壁の修理や補強には大きな費用がかかることから、その費用を見込んだ売却価格はかなり低くなります。
一軒家を売却する場合、境界の確定は重要な要素となります。
家屋内部を捜索しても、隣地や道路との間の境界確定書が発見できないことがあります。
このような場合には、境界未確定のまま、価格を下げて売却することも考えます。
売却するまでの間の管理も、一軒家の方が労力を要する印象があります。
近年の一軒家の場合、敷地内の土の部分はすべてコンクリートでおおわれていることも多いですが、古くからある一軒家の場合は土が露出していることが多いです。
春夏を過ぎるたびに草木が覆い茂り、そこに蜂なども棲みつきます。
少なくとも売却するまでの間は、剪定や害虫駆除も必要です。
一軒家に隣接している道路が私道でないか、および私道である場合には所有している部分がないか(共有持分がないか)も確認しておく必要があります。
私道が相続財産に含まれていることに気付かないまま一軒家を売却し、その後相続財産清算人業務を終えてしまうと、私道が相続人不存在のままとなってしまうためです。